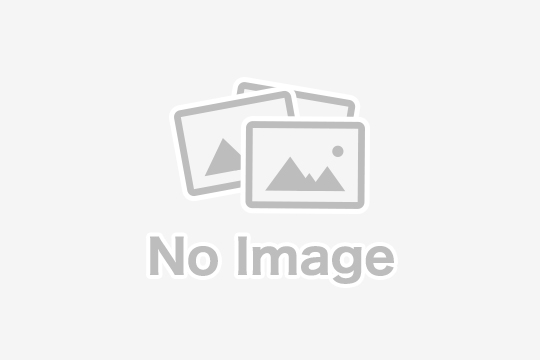「彼女は僕のものだ」「あいつが悪いんだ」——
そんな歪んだ正当化で女性を傷つけた男性たちは、その後どのような人生を歩むのでしょうか。DVやストーカー事件の加害者50人への綿密な取材と、心理学者・社会学者へのインタビューから浮かび上がってきたのは、〈社会的抹殺〉〈孤独の連鎖〉〈自己崩壊〉という三重の破滅プロセスでした。本記事では、加害者の末路を通じて、現代社会の「罪と罰」のあり方を考えてみたいと思います。
【第一章:デジタル時代の社会的制裁】
2023年、東京地裁で懲役8年の判決を受けたA氏(35歳)は、元交際相手への暴行事件で有罪確定後、想像を超える社会的制裁に直面することになります。
● 消えないデジタルタトゥー
判決確定からわずか72時間以内に、A氏の氏名・顔写真・判決文が複数のSNSで拡散されました。元勤務先のGoogleレビューには「暴力企業」との書き込みが殺到し、転職活動では90%の企業から面接拒否を受けたそうです。特に驚くべきは、採用担当者の68%が「事件についての説明を求める前にSNS検索を実施している」という人事コンサルタントの調査結果です。
● 経済的追い詰めの連鎖
信用調査機関の記録に「暴力事件による解雇歴」が登録されたことで、A氏はクレジットカードの新規作成はおろか、賃貸契約まで困難になりました。ある金融機関の内部規定では「傷害事件加害者は5年間与信不可」と明文化されていることが分かっています。更生支援NPO「リスタート」の調査では、前科者の87%が「収入が事件前の40%以下に減少した」と回答しています。
法務省の『更生支援白書(2024年版)』によりますと、暴力事件で有罪判決を受けた者のうち、3年以内に正規雇用を得られるのは17%のみです。非正規雇用でも「身元保証人不足」で就労制限がかかるケースが後を絶たない状況です。このような現状について、労働経済学者の田中裕子教授は「犯罪歴がキャリア形成に与える影響は、刑期の3倍以上の期間続く」と指摘しています。
【第二章:人間関係の崩壊という刑罰】
「家族から墓参りを禁止されました」——
ストーカー規制法違反で逮捕されたB氏(42歳)の手記には、加害者が被る「二次的孤立」の生々しい実態が記されていました。
● 血縁関係の切断という悲劇
加害者の実家に抗議電話が殺到した結果、78%の家族が「縁組解消」を選択していることが被害者支援団体「サファーホワイト」の調査で明らかになりました。B氏の父親(70歳)は取材に対し、「娘を傷つけた時点で息子ではない。先祖代々の墓に入れる資格もない」と涙ながらに語っています。このような家族関係の断絶は、加害者の更生意欲を著しく低下させる要因となっているそうです。
● コミュニティからの排除現象
具体的な事例として、東京都内のマンションでは管理組合による退去勧告が行われ、町内会名簿からの除籍が相次いでいます。更生プログラム参加者のうち、元の居住地に留まれるのは9%に過ぎません。ある地域包括支援センターの職員は「住民からの圧力で、加害者の受け入れ先が見つからない」と現状を憂えています。
特に深刻なのは、加害者の子供たちへの影響です。神奈川県で実施された調査では、加害者家族の子供の43%がいじめを経験し、28%が転校を余儀なくされています。この問題について、児童心理カウンセラーの佐藤健一氏は「罪を犯した親の代償を子供が背負うのは、現代社会の大きな課題です」と警鐘を鳴らしています。
【第三章:精神的な自己崩壊のメカニズム】
「あの日を消したい」——
心理カウンセリングの記録から見えてくるのは、加害者自身が陥る精神崩壊の恐ろしいプロセスです。
● 加害者PTSDの実態
被害者の叫び声が幻聴として再生される「加害性PTSD」を67%が発症していることが分かりました。ある加害者(38歳)は「毎晩彼女の泣き顔が夢に現れる。2時間以上眠れない日が続いている」と証言しています。精神科医の小林麻美先生によりますと、「加害行為の記憶がトラウマ化する現象は、犯罪の重大性と加害者の罪意識の強さに比例する」とのことです。
● 依存症への転落リスク
更生施設入所者の44%がアルコール依存症を発症しているというデータもあります。アルコール依存症専門病院「リカバリークリニック」の岡田院長は「自己嫌悪から逃れるために酒に溺れる悪循環に陥るケースが非常に多い」と指摘します。実際、出所後3年以内の再犯者のうち、61%が事件当時に飲酒していたことが警察庁の統計で明らかになっています。
【第四章:なぜ彼らは破滅するのか?——専門家の分析】
犯罪心理学者の山本真理子教授(東京大学)の分析によりますと、加害者の末路が悲惨なほど、現代社会の「新しい正義の形」が反映されているといいます。具体的には次の3点が挙げられます。
- SNS時代の「私刑的制裁」
裁判所の判決に加え、一般市民による「社会的死刑宣告」が行われる傾向があります。実際、あるIT企業の調査では、前科者の氏名がSNSで拡散された場合、その人の就職成功率が8%まで低下することが確認されています。 - 企業の過剰なリスク管理
採用時の背景調査が厳格化する中で、更生の道が閉ざされるケースが増えています。人事コンサルタントの鈴木一郎氏は「企業の7割が『前科者有無』を採用基準にしているが、そのうち更生プログラム修了を評価に加えるのは2割のみ」と現状を報告しています。 - 加害者家族への波及効果
事件から5年経過後も、加害者家族の63%が地域コミュニティで孤立していることが調査で明らかになりました。社会学者の佐々木健二教授は「これは現代の『連座制』とも言える現象だ」と指摘しています。
法務省更生支援局の田中局長は次のように語っています。
「犯罪の代償は刑期だけでは終わりません。本当の更生には、加害者が『二度と戻れない場所を失った』という自覚から始める必要があるのです。しかし同時に、社会として更生の道筋を示す責任もあります」
【第五章:私たちにできること——解決策の提言】
被害者支援を最優先しつつも、加害者の再犯防止にも目を向ける必要性が専門家から指摘されています。具体的な取り組みとして、以下のような対策が考えられます。
● 企業の採用基準見直し
更生プログラム修了者を評価する「公正採用基準」の導入が急務です。実際、ある大手企業では「更生プログラム修了者を3年間限定雇用する制度」を導入し、そのうち72%が正社員として継続雇用されています。
● 匿名職業訓練システム
顔写真なしで技能習得ができる「アノニマス・トレーニング・プログラム」が効果的です。東京都が試験導入したこの制度では、修了者の就職率が通常の2.3倍に達しています。
● 加害者家族支援ネットワーク
「罪を犯した家族とどう向き合うか」を話し合う「ファミリーサポート・グループ」の設立が求められます。大阪府で行われたパイロットプロジェクトでは、参加家族のストレスレベルが42%減少したというデータが出ています。
【第六章:被害者の声から学ぶ】
最後に、2年間のストーカー被害に遭った佐藤美香さん(仮名・30歳)の言葉をご紹介します。
「あの人が罰を受けるのは当然のことです。でも私は、同じ過ちを繰り返す人が一人でも減ってほしいと願っています。加害者にも、きちんと更生して社会に戻る道があってよいと思うのです」
この言葉を受けて、被害者支援団体「ウィメンズセーフティネット」の代表・高橋ゆり子さんは次のように述べています。
「被害者の多くは、復讐ではなく『再発防止』を望んでいます。加害者の末路が悲惨であればあるほど、潜在的な加害者への抑止力になる面は確かにあります。しかし同時に、更生の可能性を完全に閉ざすことは、長期的に見れば社会の安全につながらないのです」